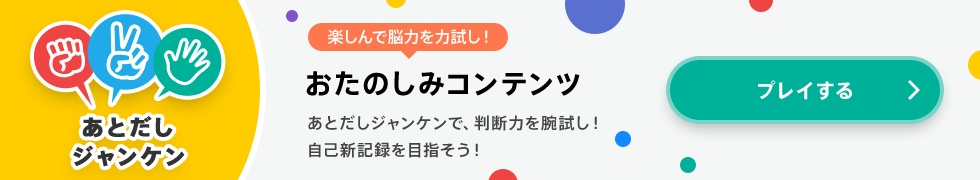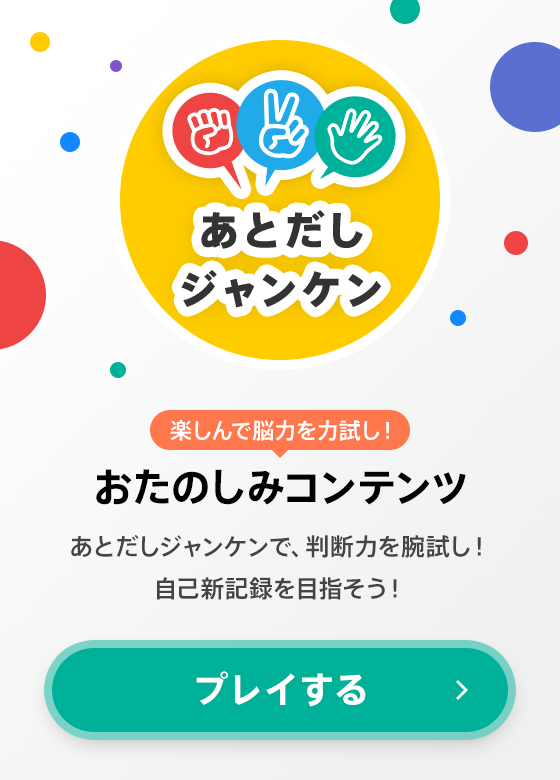水分補給は体にも脳にも重要!

※2025年7月11日リライト
私たちが生きていくために欠かせない水。実は、加齢とともに体内の水分が失われやすくなるということをご存知ですか?暑い時期は熱中症予防のために積極的に水分補給をする人も多いと思いますが、「喉が渇いた」と感じてから飲むのではちょっと遅いかもしれません。水と体の関わりを正しく知って、より健康でいるための水分補給を心がけましょう。
高齢者は脱水に陥りやすい!?年齢とともに変化する体内の水分量
私たちの身体の多くは水で構成されており、「人体の約60%が水分である」とよく言われます。
しかし、実際にはこの割合は一律ではなく、年齢や性別、体組成によって大きく異なります。
たとえば、新生児の体内水分量は約80%と非常に高く、成長とともに次第に減少していきます。
小児では約70%、成人男性で約60%、女性では脂肪組織が多いためやや低めの約55%に。そして65歳以上の高齢者になると、さらに減って約50%にまで低下すると言われています。
この変化の背景には、体内で水分を多く含む「筋肉」の量が大きく関係しています。筋細胞は水分を多く抱え込む性質を持っており、筋肉量が豊富な若年層では体内の水分量も多く保たれます。しかし、加齢とともに筋肉は萎縮し、サルコペニア(加齢による筋肉減少症)などの影響もあって筋肉量が減少。これにより、体全体に保持される水分も自然と少なくなっていきます。
さらに高齢者は、喉の渇きを感じにくくなる「感覚の鈍化」が起きやすく、結果として水分摂取のタイミングを逃しがちです。加えて、食欲の低下やトイレへの移動の負担感、夜間頻尿を避けたい心理から、意識的に水分を控えるケースも少なくありません。これらの要因が重なり、高齢者は慢性的な脱水状態に陥りやすくなっているのです。
では、体内の水分が失われると、具体的にどのような変化が起こるのでしょうか。水分が体重のわずか2%失われただけで、脳の視床下部が「渇き」を感じ始め、集中力や身体パフォーマンスの低下が起こります。
この時点ですでに「軽度の脱水」が始まっています。水分損失が4〜5%に達すると、疲労感や頭痛、吐き気、めまいといった脱水症状が明確に現れます。
さらに深刻なのは、体内の水分が減ることで血液の粘度が上がり、血流が悪化する点です。これにより血栓ができやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞など、生命に関わる疾患のリスクが高まります。特に高齢者では、もともとの血管の柔軟性の低下と相まって、その危険性は一層高まります。
こうしたリスクを避けるためにも、日常的な「こまめな水分補給」が何より重要です。喉が渇く前に意識して水を摂ること、食事と一緒に水分を摂ること、入浴前後や起床時、就寝前など体内の水分が失われやすいタイミングでの補給を習慣づけましょう。水分補給は単なる習慣ではなく、健康を守るための「予防医療」といっても過言ではありません。
水分摂取の基本は『こまめに』『少しずつ』

体内の水分は、無意識のうちに失われているもの。運動などをしなくても常に汗はかいていて、1日に約500mlもの水分が排出されています。呼吸や排泄で出て行く水分なども合わせると、成人であれば約2L〜3Lもの水分を1日で失っているのだそう。500mlのペットボトル5本分だと思うと、すごい量ですよね。
「喉が渇いた」と感じたときには、体が「失った水分を早く補給してほしい」というSOSを出している状態です。そのため、「喉が乾く前に水を飲む」ということを徹底し、脱水症状を防ぐようにしましょう。加齢とともに喉の渇きを感じにくくなるので、高齢者ほど意識的に水分を摂ることが重要です。
水分を補給するときのポイントは、こまめに少しずつ飲むこと。1日の必要量は約1.5Lなので、コップ1杯程度の水を1日に6〜8回飲むのが理想です。朝起きたときや仕事で一息入れたいとき、入浴後、就寝前などに、コップ1杯の水を飲む習慣をつけましょう。ちなみに、一度にたくさん飲んでもすべては吸収されません。それどころか体に負担をかけてしまうので、一気飲みは避けるようにしてください。
また、暑い時期は冷たい水が欲しくなりますが、飲みすぎると体が冷えたり、血流が悪くなってしまうことも。便秘や肩こりの原因になりかねないので、できれば常温のお水を選ぶことをおすすめします。
脳の80%は水分!水を飲むことで頭の回転が速くなる

水分補給は、私たちの身体全体にとって不可欠ですが、特に脳にとっては極めて重要です。
というのも、脳の約75〜80%は水分で構成されており、水は神経伝達や脳内代謝、記憶形成といった高度な知的活動を支える基盤となっているからです。
実際、イースト・ロンドン大学とウェストミンスター大学の共同研究では、被験者に500mlの水を摂取させた後、知的作業を行わせたところ、水を飲まなかったグループと比べて約14%も反応速度が速くなったことが報告されています。これは水分が脳の電気的な信号伝達や神経の働きをスムーズにし、情報処理能力を高めるためと考えられています。
また、小児を対象とした研究においても、水をしっかり飲んだ子どもたちは、注意力や記憶力のテストで好成績を示しました。これは、脱水状態がわずかでもあると、認知機能や感情の安定性に悪影響を及ぼすことがわかってきたこととも一致しています。
わずか1〜2%の水分不足でも、脳は「ストレス」を感じ、集中力の低下や思考の鈍化を招く可能性があるのです。
さらに、脳内での情報伝達には、ニューロン同士をつなぐシナプス間の電気信号が関与しますが、その過程にも水分が欠かせません。神経伝達物質の分泌や再吸収、代謝プロセスが円滑に進むためには、十分な水分環境が必要なのです。
したがって、仕事や勉強、クリエイティブな発想を求められる場面では、コーヒーやお茶ばかりではなく、「水」をこまめに摂ることが、脳のパフォーマンスを最大限に引き出すカギとなります。
特に朝起きた直後や、長時間のデスクワーク、集中力が必要な会議の前などには、意識的に水を摂取することで、思考のクリアさや反応速度の向上が期待できるでしょう。
水は、脳の“潤滑油”であり、“活性剤”でもあります。身近な「水」を上手に取り入れることが、日常の知的生産性を高める第一歩なのです。
まとめ
水を飲むことが大切だということは知っていても、忙しいとつい忘れてしまいがち。1日1.5L、つまり500mlのペットボトル3本分を目標にして、こまめに少しずつ飲む習慣を身につけることが大切です。
しっかり水分補給をして、元気に夏を乗り切りましょう!
この記事が役に立った・
ためになったと思った方は、
ありがとうボタンをクリック!
ありがとうと思った人の数114